
前ページへ
 |
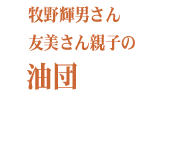 |
| 柱影映りもぞする油団かな 虚子 油団と書いて「ゆとん」と読む。油団のことが気になり出したのは、この高濱虚子の俳句を目にしてからだ。夏の季語として使われる油団は、柱影が映り込むほどにつるつるした表面をもつ和紙製品である。どうしても実物が見たくなって探した。さて、どこで作られているものやら。 その前に、まず油団について調べてみた。『広辞苑』では、“紙を厚く貼り合わせて油または漆をひいたもの。夏の敷物に用いる”と極めてあっさり。和紙のことなら何でも載っている『和紙文化辞典』(わがみ堂出版)では、“数枚の紙を張り合わせて油や漆を塗り、絵を描いたものもある。夏の敷物に用いた。パークス*の『日本紙調査報告』は大和を油団の名産地とし、『貿易備考』は、奈良県吉野町野々口のほか、福井県福井市と遠敷郡、愛知県知多郡、新潟県北蒲原郡、埼玉県熊谷、東京府下などを産地と記している”とある。どうやら昔は日本各地で作られていたものらしい。 *
ハリー・パークス(Harry Smith Parkes)
|
||
 |
|
|
|
今では油団を作ることができる唯一の店、表具店『紅屋 紅陽堂』の牧野輝男さん、友美さん父子を福井県鯖江市に探し当て、油団の制作の一場面を見せていただき、お話を伺うことができた。幸運だったことは、油団の制作は一年に一度だけ、4月から始めて6月には終わるということで、ちょうど6畳の油団を作り始めるところだったことだ。今年はもうこれ1枚だけ、と牧野さんはおっしゃる。作るのには広い場所が要り、手間がかかる、天日に干すには屋根に持ち上がらなければならない。こうした諸々の制作上の制約のため作り手が減ったことも消滅の一因ではあろうが、日本の夏から油団が姿を消したのは、私たちのあんちょこな涼しさを求める生き方でもあっただろう。大都会の夏は、室外機から吹き出される熱気で、窓を開けても涼風が通り過ぎることはなく、とてもクーラーなしでは寝つくことができない。でも、私たちはそれが健康によくないばかりか、自然を傷めていることにも気づきはじめている。まずは、生漉の和紙が敷物に変身するまでをご紹介しよう。 |
||
打ち刷毛で"どんどん" 工房の入口に足を入れると、どこからか"どんどん、どんどん"と腹に響かんばかりの音が聞こえてくる。音源を辿って2階に上がってみると、紅屋3代目の友美さんが分厚い刷毛で、床に広がる真っ白な和紙の一端を叩いているところだった。 手順としては、床の上の油団台という和紙に柿渋をひいたものの上に、70cmX50cmほどの楮100%の傘紙を重なりがないよう、6畳なら6畳分の一枚紙に貼り合わせてゆく。一枚貼るごとに丹念に“どんどん”“どんどん”と、打ち刷毛で打つ。シュロでできた重量感たっぷりの刷毛を、しゃがんだ姿勢で持ち上げ、力を入れて垂直に紙に落とす作業は大変な力仕事だ。この重たい刷毛で叩くと、下の紙と繊維がからみあうようになるのだそうだ。 |
 |
|
| 貼り重ねる枚数は13〜15枚が目安。紙に糊をつける、貼り合わせる、刷毛で叩く、といった一連の作業は、熟練の技と息のあったチームプレーが要りそうだ。和紙にぬる糊も多すぎても少なすぎてもいけない。代々、奥様の役目というのもうなづける。貼り重ねる作業は紙の上に乗って行うので、汗をかく時期、素足ではまずいし、スリッパでは力が入らない。一番いいのは竹の皮で作った草履であることがわかった。油団台に貼りつけてゆく作業も、極くわずかずつでもずれてゆくと、6畳の端の方までくると大きなずれになってしまう。初代に技を叩き込まれた2代目輝男さんがやると、ずれは8畳ものでも3mm以内に納まるという。一辺360cmに対して3mm以下というのは驚異的だ。下に線を引いておくわけでもなく、目と勘だけが頼りの作業。単純な作業ほど難しいという、もの作りの原点がここにもあるような気がした。 | ||
窓にひらめく赤い紐 和紙の厚さにより異なるが、だいたい13〜15枚が貼り重ねられると、えごま油を手で塗ってゆく。硬化油なので手が熱い!と感じるくらいの温度にまで上げて、布を使って2度塗りする。裏には柿渋を撒く。そして、たっぷりえごま油を吸い込んだ3坪10平米の一枚紙を乾かすのがまた一苦労。一日中快晴であろう日を狙って、3人かがりで屋根まで持ち上げる。だから梅雨がくる前に仕上げなければならない。 |
 |
|
| 一度は屋根からつるりと落としてしまい、だめにしてしまったこともあるという。大敵は鳥。糞を落とされたらもう直すことができない。鳥よけの赤い布を針金に結んで渡して、後は鳥が上空から糞を落とさないことを祈るばかり。 開け放たれた作業場の窓にも、赤い紐が何本も吊り下がっている。窓を開け放して作業するので、鳥が飛び込んでこないためだそうだ。また、この頃は作り手も年をとってきて屋根に運びあげるのが危ないので、室内で干すようにしているという。 3mmほどの厚さに打ち合わされた油団は、冬場は丸めて納屋などに保管されることが多い。季節が巡ってきて再び広げた時、端がめくれあがり足をとられるようなことがないため、専用の留め金も考案されている。薄めで堅い油団が上質とされ、良質の和紙を使うことと、油をたっぷり染み込ませることが肝要。牧野さんの作る油団は、広げて暫くするとぴたっと畳に添い、端がめくれることはないという。修理のために持ち込まれた古い油団は、しみ一つないものから、端がちぎれていたり、数カ所に穴があいているものまで。油団の運命も使う人次第というわけだ。 私の訪問にあわせて昨日広げた、とおっしゃる30年以上たつという油団は、すでにしっとりと畳に馴染み、庭の緑陰を映しこみ、逆光をうけて艶めかんばかり。 |
||
 |
時代のたった細かな編み目の藤の敷物も美しいし、漆を拭き込んだ欅の床も美しい。しかし、油団は、和室にふさわしい敷物として、今までに見たこともない種類の美しさを持っている。 牧野さんは、子供の頃、よく親に、油団のうえで昼寝をすると風をひくよといわれたものだとおっしゃる。数年前、福井テレビが室温と油団上の温度をセンサーで計ったところ、油団の上は室温より2度低かったという。和紙の力、恐るべしである。 |
|
 もう作らないのですか? 牧野父子の口ぶりからは、世の中が必要としなくなった油団は、もう作る必要はないんじゃないか、という雰囲気が伺える。作るほうの苦労ばかりではなく、使うほうも、2日にあげず乾拭きをしたり、糠袋で拭いたり、涼風のたつころには丸めてしまったり、初めのうちは水分をこぼしたままにしておくとシミになったり、重い家具をのせておくと型が残ったりと、世話が焼ける。しかし、初めは白っぽかった油団が、次第にあめ色に変化し、堅く丈夫な表面をもつようになり、それからは水をこぼしても、家具を置いても大丈夫。手作りのものは、手をかけて育てるという心意気があってこそ、美しさを引き出すことができるというが、油団もそのようだ。作り手の制作能力にちょうどみあうくらい、油団を欲しいという人が居て、この手仕事の技が消えてしまわないことを願うばかりだ。 (2002/5) |
||
|
|
