
 |
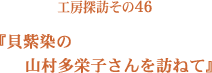 |
 |
紫という色は、人類が色を染める技を発見したときから、特別な色として好まれてきたと言われています。紀元前1600年には、クレテで貝から紫色が染められていたとの学説があり、そのパープル染料の本家本元と考えられているフェニキアのタイレという町の特産品がパープル染料である、との記述が聖書にあり、紀元400年頃の、羊毛で織られた布に紫色の糸で刺繍がほどこされたエジプトの着衣も見つかっています。あのクレオパトラが紫の衣を好んだと言われるのには、神学者、歴史学者、考古学者らの研究の裏づけがあり、その後も、中世から現在に至るまで、権威や象徴性を求めて為政者、聖職者らが紫の衣を纏うのは変わっていないようです。因に、日本では弥生時代の吉野ケ里遺跡から染色物が発見されています。 巻き貝の体内にあるパープル腺の分泌物から得られる紫色は、かくもいにしえから、かくも熱狂的に求められ続け、いまだに絶大な魔力を失っていないようです。 |
 |
 |
|
染織作家山村多栄子さんは、父親の赴任先であった韓国の仁川(インチョン)に生まれ、終戦とともに7歳のとき故郷の山口県に帰国。その後上京、東京で結婚、ほどなく染め織りを始めました。少し習ったきりで織りの技術もよく知らないうちに織り機を注文してしまい、本を見ながら独学で“組織”をおぼえたといいます。植物染織は山崎桃磨氏に学びました。まだ道具の揃わなかった頃、ご主人に糸束の端を持ってもらって深夜まで男巻きを巻いたこともあるとか。昭和47、8年頃の着物ブームといわれた時代には、草木染の紬の着物が人気を博し、制作に追われる多忙な日々を過ごしました。 貝紫染に取り組み始めたのは7、8年前から。その染め方は、フェニキア人のそれと大差のない方法。まず、貝を入手し、硬い殻を割り、極少量のパープル腺を取り出し、苛性ソーダを加えて藍を建てるようにして染液を作ります。美しい色をだすための新鮮な貝の入手、分厚い貝殻を割る苦労、手のひらサイズの貝からとれる分量は茶さじ1杯程度、水に溶き過熱すると独特の悪臭を放つという具合に、貝紫染は草木染よりも何倍も手間がかかり、困難の多い作業です。着尺1反分を染めるのに50kgからの貝が必要です。使う人が限られていれば、貝を採集する専門業者もいない、漁のとき網にかかってきた貝を集めて送ってもらい、タイミングを図るようにして素早く作業を行わなければなりません。取り出した分泌腺の内容物はクリーム色。それが、紫外線に当たることと酸化によって、ブルーから紫色へと変化し、褪色することのない深い赤紫まで、多様なグラデーションが得られます。染材の希少性と作業の困難さから、でき上がった織物は非常に高価なものになってしまいますが、そうした苦労にもめげず貝紫染を続けてきたのは、山村さんも、この貝紫の紫色の不思議に魅せられた一人ということなのでしょう。 |
 |
 |
|
染織作家として日本工芸会などの公募展などに入選を重ねる一方、山村さんにはプロデュ−サ−的な役割があります。お住いが八王子という染織産業が盛んな土地柄もあり、東京産の蚕から得られた絹糸の普及をしている『東京シルクライフ21研究会』というグループに参加しました。10年前には東京近郊に50軒ほど残っていた養蚕農家が、現在はわずかに2、3軒。大手繊維メーカーは中国をはじめブラジルに技術指導を行い、量産品としては充分使用に堪える品質の糸を生産できるようになり、国内の養蚕農家は立ち行かなくなりました。山村さんらは、東京産の絹糸が絶滅することのないようにと、着物やスカーフ、服地をデザインし、八王子の機屋に織らせ、流通に乗せる努力を続けているというわけです。また、目にも鮮やかなグラデーションが美しい手作りの刺繍糸も、特別に欲しい方に販売しています。 貝紫染の活動では、6年前から2年に一度、貝紫展を有志12名で開いています。貴重な資源である日本のアクキガ科アカニシ貝が乱獲されないよう、かつ、貝紫染の技法が守られるようにとの主旨で活動されています。山村さんは、これからも紫の色を楽しみながら、マイペースで貝紫染に取り組んでゆきたいと考えています。 |
 |
 |
| (2006/8 よこやまゆうこ) |
|
(C)Copyright
2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |