
 |
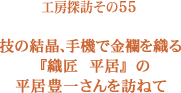 |

|
side story173でご紹介した小野内織物所の小野内さんにお連れ頂いて見学した手織り金襴の『織匠 平居』を改めて訪問しました。4代目を継ぐ平居豊一さんは、伝統工芸士として卓越技能賞を受けた職人さんであり、老舗織元の経営者です。特殊な分野の裂を作るご苦労や愉しさを話して下さいました。 平居さんのお話は、翌日に控えた大峰山参詣の話から始まりました。朝4時に起きて、奈良県の大峰山を目指し、標高1700mの修験道を辿ります。この行の最終難関は、300mほどの断崖絶壁の上に、3人の仲間に足を支えられ、下を覗きこみながら先達の問いに答えるという「覗き」修行。最後に、ずるりとロープが弛められ、身体が谷底へ落ちそうになる、という恐怖体験。他者を信じて身を委ね感謝を忘れないことを体験するというもの。平居さんは、今年で41回目。すでに80人からの新人のまとめ役です。40余年と言う長い年月、欠けることなく参加してこられたのは、行者さんの“お受け”があったからだと思っているそうです。 |

|  |
| 『織匠 平居』が金襴を織るようになったのは豊一さんの代から。父、祖父は帯の裏地や子供の結帯の裂、茶道関係の裂を織っていました。この世界では仕事の仕方に3種類あり、一つは、材料の絹糸や金箔を与えられて織ることだけに専念する賃織り、もう一つは、仕込み機と呼ばれ、自ら原材料を調達するけれども納め先は織りの業者、そして材料調達をし問屋に卸す自前の織屋の3つ。平居さんは自前の織屋です。25歳のとき、自分で考案し織った裂が先方に気に入られたのをきっかけに、仕事の愉しさを知ったとおっしゃいます。紋屋と呼ばれるジャガードのパンチカードを作る専門職や、糸の染屋と相談しながら、幅70cmの裂を作ります。宗派や寺独自の定紋があるので、同じ裂をどのお寺にも、というわけにはゆきません。紋紙は裂一枚毎に一組が必要で、工房の天井近くまで積み上げられた紋紙の山が、そのことを物語っているかのようです。 桐箱に入った一枚の古い袈裟を見せて頂きました。高野山にある真言宗の寺から復元を依頼されました。色の焼け具合、糸の劣化具合からも、何十年も使われてきた袈裟であることが推測されます。まだジャガードが導入される前の、人が機の上で柄出しを操作していたころの裂だろうと推測されるそう。復元の手順は、まず紋屋に古い袈裟の模様から紋紙を作らせ、糸を染屋に発注し、ふさわしい金糸、金箔を入手し、材料が揃ったところで1ヶ月ほどかけて織りあげる。平居さんの役目は、プロデューサー兼織り手といったところでしょうか。 |

|  |
| 金襴の織り自体についても不思議なことがいっぱいでした。天井に届きそうなところにある機の先端から紋紙が吊り下げられ、ペダルを踏むと紋紙とおりに綜絖が動き、緯糸の入る位置が決まります。その数30枚という綜絖。竹製の1cm幅ほどの細長い篦(へら)で金箔を引っかけ、緯糸の間に挟み込んでゆきます。その手さばきの早いこと!織れた布は、裏面が表として使われるため、セットされた小さな鏡で間違いがないかチェックしながら織り進みます。もう一つ、見慣れない作業がありました。手元に巻き込まれてゆく20cmほどの裂に、袋にいれたふのりを絞り出しながら塗ってゆくのです。模様のゆがみを起こさないためと、切ったときにほつれないようにするためです。長い時間の中で工夫され改善されてきたさまざまな技の結晶がありました。金襴の重厚さ、豪華さは、細い糸の幾重もの重なりが織りなすブロケードならではの迫力を感じさせてくれます。 |

|  |
| 平居さんの独創的な遊び心が発揮された一品を見せていただきました。玄関先に何気なく置かれている衝立と額絵。曲尺一寸間90本に裁断した本金箔を使用した織物。しかも、紋織に加えて“すくい”の技法が使われていて、つづれ織独特のテキスチャーを生んでいます。このような技法の合体された織物は、平居さんご自身も、ほかに聞いたことがないそうです。 二人の息子さんが跡継ぎとして育っている『織匠 平居』は、宗教関係の裂だけでなく、新しい分野の織物を織り出してゆく可能性を感じさせてくれました。 |
 |
| (2007/8よこやまゆうこ) |
|
(C)Copyright
2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |