
 |
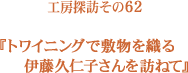 |
 |
湘南の風が快い住宅街のお宅、急な階段を登るといきなり天井から吊された緞帳のような分厚い布に対面します。横2、9m、縦2、6mの竪機の大迫力には圧倒されるばかり。伊藤さんはその前に座り、スツールを左右に移動しながら、経糸一本ごとに緯糸を手でもじってゆき、一段終る毎に経糸と緯糸を落ちつかせるためにビーターで叩きます。機織りとはいえ、杼も筬も綜絖もありません。この技法の名はトワイニング(横もじり織)。織るというよりも経糸に緯糸を絡ませるといったほうが近いようです。段が進めば、足場に登り天井近くまで織り続けます。経糸は上下で固定されており、織り上がった部分を巻きとってゆくことができないので、自分の位置を上へ移動しながら織ってゆくからです。この織り方は初めて見るものでした。 |
 |
 |
空中浮遊の達人は、もと保健体育の先生。14年間も高校で跳んだり走ったりころがったりを教えてきたのですから、2mほど浮遊することなど容易いことなのでしょうか。疑問は、何故、体育教師が手作りの仕事に転向したかです。学生時代から体育と美術の成績はいつも良かったそうで、教師のかたわら習い始めた織物が本職に移行していったことも、いたって自然のなりゆきだったと話されます。工房で織りを習っている時、心から心地良さを感じ、次第にそれに賭けてみたいと思うようになったそうです。お住まいの茅ヶ崎から、師であるテキスタイルアーティスト徳重恵美子氏の大磯のアトリエに通う生活は楽しく、結局5年間アシスタントとして過ごしました。 一人での制作作業が始まり、1992年、高岡クラフトコンペに入選したことを弾みとして、2年後に初個展。ままだまだプロの意識は薄く、素人の一度限りの個展、という心境だったとおっしゃいます。これが手仕事の作り手たちをプロデユースする人の目にとまり、デパートでの展示会に参加、その後もさまざまなクラフト展に入選、個展も回を重ねました。昨年の京都での個展ではほぼ完売。糸偏には厳しいといわれる京都での高い評価は、何よりもこれからの作品作りへの力となりました。 |
 |
 |
| 伊藤さんは大物がお好きです。ウールを堅く打ち込んでいる敷物はずしりと重く、30キロ近くになるものもあります。まずは小さいものから、との発想はまったくなく、独立当初からフルサイズの敷物に取組み、6枚仕上げての初個展でした。先生のところではもっと大きなものを作る手伝いをしていたので、サイズに幻惑されることは少しもなかったというのですから、頼もしいかぎりです。 糸は山羊、ラクダ、羊、ヤク、麻、絹など。いろいろな種類を7〜8本ひきそろえて織ることが多く、なかでも山羊の野性的な硬い毛が好きだとおっしゃいます。経糸も木綿ではなく、ノルウエーのウールで試してみたところ、緯糸の食い込み具合がよいのでそれ以来、ずっとウールにしています。素材の自然の色の違いをデザインに取り入れることが多く、草木染の糸を加えて作ることもあります。 独立して工夫したことの一つが、敷物のデザインによくあるボーダー柄をやめたことでした。長方形の敷物が長方形で終らず、視覚的な広がりを持たせたいと思ったかったからです。もう一つは、ひきそろえた緯糸を2束でやっていたところを、3〜4束にして展開することにしたのです。これにより模様の可能性が広がりました。一旦決めたデザイン通りに織るのではなく、そのときの気分で緯糸に変化をつけ、模様をいれます。敷物から離れて眺めては全体のバランスを見、どのように模様を変えようか、などと考えながら織るのが楽しいとおっしゃいます。 |
 |
 |
 |
伊藤さんの敷物の魅力は、何と言ってもその存在感にあります。素材を最大限に生かすことを第一に考えているとおっしゃるとおり、動物が身にまとっていた毛という物質の存在感が迫ってきます。それは、麻や木綿、絹とも違う、哺乳類の体温というか、人間と同質の何か、とでもいうようなものでしょうか。フローリングの床に敷けば、犬も猫も人も、ごろりと寝転びたくなりそうです。 毎朝一番にすることは、縦機の前に佇んで10分ほども眺めること。きっとウールたちの語りかけてくる声を聞いているのでしょう。素材に素直にをモットーにしている伊藤さんの心が、その声をくみ取るのだと思いました。お米用の紙袋に入って押入に積まれているさまざまな糸が、敷物になって次の個展会場に並ぶ日が楽しみです。 |
| (2008/10 よこやまゆうこ) |
|
(C)Copyright 2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |