
 |
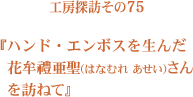 |
 |
1979年というと、日本は高度成長期が終わったあと、庶民の暮らしがさらなる円熟をめざしていた頃ではないでしょうか。グラフィックデザインを学んだ花牟禮亜聖さんは、日本橋高島屋宣研に入社しました。専門職への女性の採用はまだまだ稀だった時代のなかで、紅一点の採用でした。生活に関わるデザインを志した女性の、その後の幸運な歩みを取材しました。 |
 |
 |
  |
初めての職場では、次々と輸入される上質で洗練されたヨーロッパ高級品の広告制作に携わりました。ここでは、老舗の歴史や背景を知ることを通じて知識を得、ブランド品をその手で確認することで、本当に良いものへの目を肥やしてゆきました。 けれども、3年もしたころから、二週間単位で消えてゆく広告デザインに明け暮れることに疲れを感じ、“残るものを作りたい”との願いを持つようになってゆきました。 そんなときに出会ったのが『il palloncino rosso』というイタリア人女性作家Iela Mariさんの描いた絵本でした。26歳の花牟禮さんは、紹介状一通をもってイタリアに渡り、マリさんの門をたたきました。マリさんは、突然飛び込んで来た東洋の女性が、つたない英語で示す熱意にほだされながらも、“イタリア語がしゃべれるようになってから来なさい”と。特訓の語学習得ののち、マリさんはデザイナーBruno Munari氏を紹介してくれ、週2、3回、出入りすることがかないました。ムナーリ氏がアシスタントを採用したのは初めてのことでした。若さゆえの行動力、まっすぐに伝わってくる熱意が、花牟禮さんに道を開いたということでしょうか。 アトリエでは、使い走りのようなことから始まり、ムナーリ氏の“子供のような感性”を目のあたりに吸収することができました。ムナーリ氏のところで学んだ一番大きなことは、と伺うと、“素材をあらゆる方法で変化させて、なにかを創ること”だそう。“他人の作品と自分の作品が偶然似てしまっていても、1000回続けて制作すれば、それは真似ではなく自分のものになる”との氏のアドバイスを、彼自身のやり方を通じて受けとりました。これは真に、伝統工芸の世界にも通じることでしょうか。 マリさんとは、共に植物のスケッチをしたり、ボローニャの絵本展に出品するための手作りの本を作る手伝いをしました。 渡伊の翌年には、ポスターのコンクールPremio Sanfedele(プレミオ・サンフェデーレ)に応募。何と、いきなり大賞と賞金100万円を獲得してしまいます。この賞金の使い道は、ペルージアで親しくなったおばあちゃんのレシピ本の制作にそっくり使ってしまったというからあっぱれ。 帰国したその年、野菜のシルエットのハンド・エンボスの作品で銀座ギャラリーノムラで初個展。確かな手応えを得ました。イタリアでのたった2年間に、人生の方向を決める師に巡り会い、大きな賞を獲得、東京での個展という具合に、短期間でのラッキーなスタート。花牟禮さんは、きっと、今風に言う“何かを持っている”方と思わずにはいられません。 |
 |
 |
|
 |
 |
|
「ハンド・エンボス」とは、聞き慣れない用語です。エンボスは、版をプレス機で押し素材に凸凹面をつくる技法のこと。それをすべて手作業でするというのが、花牟禮さんが生み出した技法です。2010年11月の個展では、八ヶ岳の山野草をスケッチし、細かな茎、葉、花の表情を表現した作品が並びました。一見、やさしそうに見える作業ですが、一つの作品に50を超えるパーツが使われています。それらをライトテーブルの上で、奥から手前に凸凹をつけながらエンボスすることで、奥行きを出してゆきます。その順番を見極めるのも難しそうだし、一つ一つをスタイラスという道具で押し付けてゆく作業も、恐ろしく根気と集中力のいる手業です。紙は、試行錯誤の末に漉いてもらう雪晒しをした富山の楮100%の悠久紙が最適だとおっしゃいます。 |
 |
 |
| 現在は大学で後進の指導にあたり、紙の素材にこだわったデザインの仕事をしています。建築家のご主人と日本画家を目指す息子さんとの健やかな暮らしを、花牟禮さんは心から楽しんでいらっしゃるようです。 |
 |
 |
| (2011/1 よこやまゆうこ) |
|
(C)Copyright 2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |