
 |
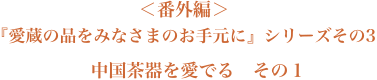
|
| 写真をクリックすると拡大します |
|
side story #464でお知らせした断捨離シリーズその3です。 一時期、中国通の友人の影響で、中国茶に傾倒したことがありました。都内専門店に通い、実にたくさんの種類があることを知りました。日本の茶道のような「道」と名のつく格式や作法や精神性はないながら、もっぱら味と香りを追求する中国人の嗜好品へのこだわりの一端を垣間見ました。 岩茶の王様といわれる「大紅袍(だいこうほう)」なる茶があることを知りました。それは、中国・福建省にある2000メートル級の奇岩が林立する武夷山(ぶいさん)にある樹齢300年を超える2本の茶樹。得られた茶葉は昔なら皇帝、今なら一部の権力者のみ味わえるものであって、その樹の孫木からの茶葉でさえ垂涎の的とされている、云々。 好奇心猫殺すのことわざもなんのその、国内線小型飛行機に乗り、その樹を一目見る旅に出ました。記憶が正しければ、武夷山は北半球で2番目に大きいとされる1つの岩からできた山であるとのこと。中国画がもっぱら縦長に描かれることを心の底から納得しました。それほど360度ひらけた風景は、縦が強調された山々でした。 中国人なら生涯に1度は登りたい、とされる人気の山だそうで、岩を削り出した細い急な階段では、立ち止まることさえできないほど陸続と後ろから登ってくる中国人。その気配に、周囲の風景を眺める余裕もありませんでした。辿り着いた頂上の広場では、濃茶色になるほどお茶で煮込まれた茹で卵(茶葉蛋)が売られており、たいそう美味であったことを思い出します。 峰の違う山筋の中腹にある大紅袍の老樹は、見慣れている日本の茶畑とは違い、石積みの段々になった一隅に、何ということのない風情でぽつんと2本立っていました。由来を説明する看板があるわけでもなく、柵に囲まれているわけでもなく、言われなければ、ちょっと大きなお茶の木ね~と通り過ぎてもおかしくないような、、。枝を持ち帰り接木をしようとする人もいないと思われていたのでしょう。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
石の色や質感を愛でた中国人のアイディアと技の粋とされる「翠玉白菜」は、國立故宮博物館の目玉となっていますが、彼らの石への強い関心とウイットに富む眼差しを感じる逸品をご覧になった方も多いことでしょう。 今回ご紹介するのは、光沢のある黒い石から彫り出されたものと、薄い朱泥で作られたもの。旅の途中の骨董店で見つけたユーモラスな魚を模した急須。決して高級なものではないながら、お茶好きな人のコレクションとして愛でられた品だったのでしょう。遊びこころたっぷりの意匠に惹かれました。 |
|
ご購入にご興味のある方はお気軽に shop@handmadejapan.com までご連絡ください。 |
|
このシリーズ、どこまで続くかは不明ですが、ものとの出会いを記しながら、みなさまに使っていただけたらと願いつつ販売いたします。 シリーズその1 ベネチアングラスの皿 シリーズその2 クバ族の草ビロード シリーズその3 石の中国茶器 その1 |
| (2025/4 よこやまゆうこ) |
|
(C)Copyright 2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |